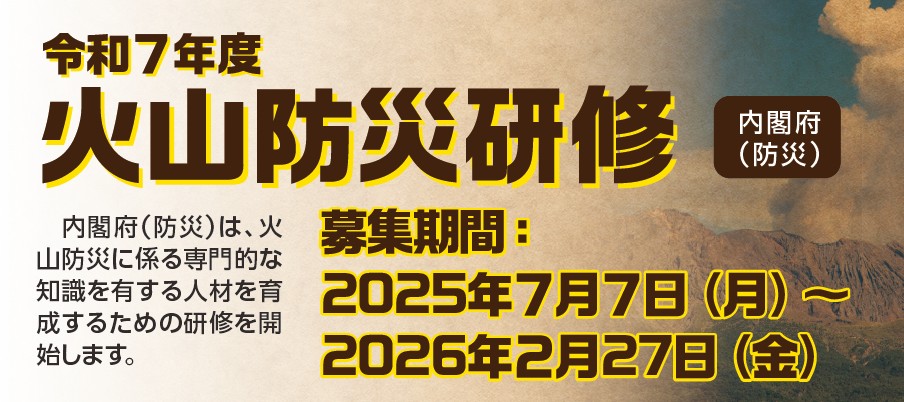
※横にスクロールできます
| テーマ | 研修内容 | 講師 |
|---|---|---|
| ①基調講演 | 火山学・火山防災に造詣が深い第一人者より、自身の過去の研究にまつわる経験談を聞き、火山防災の歴史や思いに触れる。 | 藤井 敏嗣 山梨県富士山科学研究所 所長 東京大学名誉教授 (理学博士) |
| ②火山防災業務概論 | 避難計画や警戒避難に関する助言を行うには、法体系や地域防災計画の位置付けについて熟知しておく必要がある。そこで、活動火山対策特別措置法や地域防災計画の位置付け等について理解する。 | 山田 拓 内閣府 政策統括官(防災担当)付 参事官(調査・企画担当)付 参事官補佐 |
| ③火山現象や噴火警報等に関する基礎知識 | 火山噴火時の避難計画は、気象庁の発表する噴火警戒レベルと連動している。火山現象の種類、噴火警報や噴火警戒レベルの考え方、火山噴火時の情報伝達について理解する。 | 新堀 賢志 特定非営利活動法人 火山防災推進機構 理事 事務局長 (博士(理学)) |
| ④火山地域のハザードマップとその活用について | 火山噴火に伴い避難行動をとる場合や避難計画を事前に作成する際には各火山現象の被害想定範囲を明示したハザードマップを活用することが必要であり、その基本的な考え方と活用方法について理解する。また、降灰後の土石流に対する土砂災害緊急情報についても理解する。 | 大野 宏之 一般社団法人 全国治水砂防協会 理事長 (内閣府火山防災エキスパート) (博士(農学)) |
| ⑤避難計画作成の考え方 | 火山防災協議会では噴火シナリオや影響範囲をもとに避難計画を作成する必要がある。また、避難促進施設における避難確保計画作成にあたっては、市町村が支援する場合もある。それら災害予防の観点で必要となる考え方を理解する。また、離島へき地、複合災害、広域避難など地域ごとに考慮すべき点は多様であり、その考え方も理解する。 | 新堀 賢志 特定非営利活動法人 火山防災推進機構 理事 事務局長 (博士(理学)) |
| ⑥訓練実施の考え方 | 他災害と比較して発生頻度の低い火山災害に対して、計画に則り職員一人一人が的確に対応するには訓練等を通じての人材育成・確保が課題である。防災訓練の実施等を通じて職員の災害対応経験の不足を補うにあたっての考え方や専門家としての心得を理解する。 | 吉本 充宏 山梨県富士山科学研究所 研究部研究管理幹 (博士(理学)) |
| ⑦火山災害の減災対策 | 火山噴火災害の被害を軽減するための緊急的な減災対策の計画と事前準備及び緊急対策工の機能と限界について理解する。 | 山越 隆雄 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 砂防計画課地震・火山砂防室 室長 (博士(農学)) |
| ⑧過去の災害に学ぶ | 火山噴火前後においては、避難者の一時帰宅のタイミング等課題は多くあり、過去の対応事例を学ぶ。 | 島田 明夫 東北大学 名誉教授 (内閣府火山防災エキスパート) (博士(工学)) |
| ⑨火山の恵み | 火山地域は観光地域と併存している箇所も多く、防災と観光の両立は各地で課題とされている。ジオパークとの連携や観光客・登山者を対象とした普及・啓発の考え方などについて理解する。 | 杉本 伸一 雲仙岳災害記念館 館長 (内閣府火山防災エキスパート) |